フラッシャー製作講習会資料
'98.11.28
1゜はじめに
ソーラーカーに適した省電力型のウインカーを提供することが目的です。
このフラッシャーのシステムは、LEDを用いた発光モジュール部と、方向指示器のスイッチ、そして、電流を自動的にオンオフするフラッシャー回路により構成されます。
2゜特徴
・発光モジュール部は、高輝度LEDを使用して低消費電流で動作します。また、定電流回路を用いたことで、バッテリー電圧が変化してもLEDの明るさが一定になるように動作します。
・フラッシャー回路は、負荷となる発光モジュール部をつなぐと動作を開始するようにし、配線本数を極力少なくしています。また、フラッシャー回路を工夫して消費電流を押さえ、待機時1μA以下、動作時1mA以下で機能します。
3゜回路の動作
・発光モジュール部
定電圧ダイオード(D5)で一定の電圧(5.6V)を発生させ、トランジスタ(Tr2)のベースに一定の電圧が掛かるようにします。このときトランジスタのエミッタ側の抵抗(R10)で制限される電流が流れます。この電流はトランジスタのコレクタ電圧が変化してもほぼ一定です。電流値は、エミッタ抵抗(R10)に掛かる電圧が5Vで一定となるので、(LEDの電流)=5V/(R10の抵抗値) となります。
R10が150ΩのときLEDの電流は33mA、200Ωのとき25mAになります。
R11には1、2mAの電流が流れるようにします。バッテリー電圧が48VではR11は33kΩ、24Vでは10kΩとします。
LEDの特性の例を表1に示します。LEDに流す電流は最大電流値以下にします。
モジュール1つあたりのLEDの個数は、バッテリーの最低電圧を考慮して決めます。
(LEDの個数)≦((バッテリーの最低電圧)−8V)/(LED1個の電圧:2V)
たとえば、バッテリー電圧が48Vのシステムで、バッテリーの最低電圧が38Vとすると、LEDの個数は15個以下となります。ここで、LEDを30個並べたいときには2回路分のモジュールを並列にします。
・フラッシャー回路
スイッチの操作で発光モジュール部を接続するとFETがオンオフの動作を開始します。ごくわずかな電流で動作するC-MOSのICを使っています。
このICは、4個の2入力NANDゲートで、2つの入力をつなぐとインバーター(反転回路)として動作します。入力インピーダンスがきわめて大きいのが特徴で、通常は入力に電流が流れません。入力電圧が閾値電圧(VTH)より低いときは出力電圧がVDD、入力電圧が
VTH より高いときは出力電圧が0V(VSS)となります。また、入力電圧が
VDDより高いときや、0V(VSS)より低いときには、IC内蔵のクランプダイオードにより入力端子に電流が流れます。
動作を説明するため、図1に回路の信号波形を示します。
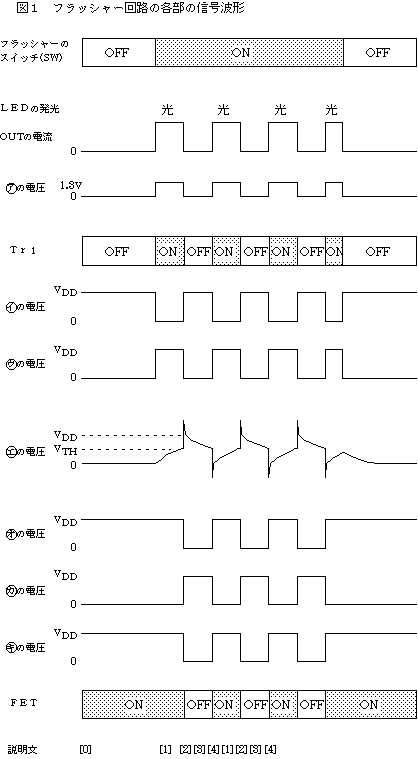 |
[0]
フラッシャー回路が待機している時は、OUTにつながるスイッチ(SW)がオフで、LEDは消えています。このときすでにFETはオンの状態になっています。
[1]
SWをオンにすると、LEDに電流が流れ、(ア)に約1.3Vの電圧が生じます。そのためTr1のベースにも電流が流れTr1がオンします。(イ)の電圧は0Vになり、(ウ)の電圧はVDDとなります。R2を通じてC1が充電され、(エ)の電圧が徐々に上がっていきます。
[2]
(エ)の電圧がVTHに達すると、(オ)の電圧が下がり(カ)の電圧が上がります。すると、C1を通して(エ)の電圧が急激に上がり、(オ)の電圧は0V、(カ)の電圧はVDDとなります。このとき、(エ)の電圧は一瞬VDDを越えますが、R3とC-MOSのIC内蔵のクランプダイオードを通して電流が流れ、すぐに電圧はVDDとなります。また、(キ)の電圧は0Vとなり、FETはオフとなります。
[3]
FETがオフのため、LEDに電流は流れず、(ア)の電圧が0V、Tr1のベース電流が0、Tr1がオフします。(イ)の電圧はVDDとなり、(ウ)の電圧は0Vとなります。R2を通じてC1が放電され、(エ)の電圧が徐々に下がっていきます。
[4]
(エ)の電圧がVTHまで下がると、(オ)の電圧が上がり(カ)の電圧が下がります。すると、C1を通して(エ)の電圧が急激に下がり、(オ)の電圧はVDD、(カ)の電圧は0Vとなります。このとき、(エ)の電圧は一瞬0Vより下がりますが、R3とC-MOSのIC内蔵のクランプダイオードを通して電流が流れ、すぐに電圧は0Vになります。また、(キ)の電圧はVDDとなり、FETはオンとなります。
[5]
このとき、LEDに電流が流れ、[1]と同じ動作で(エ)の電圧が徐々に上がっていきます。
以上の繰り返しで、FETはオンオフ動作を繰り返し、LEDが点滅します。
点滅周期は、T(秒)=1.4×C1(μF)×R2(MΩ) です。
・R9とD4について
5V〜10Vの電圧を直接供給できないときには、R9とD4を用いて、10Vの電圧を作ります。R9は、バッテリー電圧が48Vでは33kΩ、24Vでは10kΩとします。
・R8とD3について
オンとオフの時間の比を変えたいときに、R8とD3を取り付けます。これを付けることで全体の周期も変わってしまいます。詳しくは付録の計算式を参照して下さい。
4゜製作上の注意
・静電気に弱い部品
IC(C-MOS)は、回路につながっていないときは静電気で特にこわれやすいので、アルミ箔や静電防止袋で保管します。作業の時は静電気を逃がしながら作業します。FETは少しは丈夫ですが静電気に注意した方がいいです。
・極性、向きのある部品
ダイオード、LED、トランジスタ、FET、電解コンデンサー(C3、長い方が+)には極性があります。
IC、ICソケット、ニチアツ端子には向きがあります。
抵抗とコンデンサー(C1,C2,C4)には極性はありません。
・半田付け
半田ごては、半田クリーナー(耐熱スポンジに水を浸したもの、なければ濡れ雑巾で代用可)で、時々こて先の汚れを落としながら作業します。
プリント基板の半田付けしようとする場所に半田ごてを当て、それから(1秒くらい後に)ヤニ入り半田を当てると半田がきれいに流れて良い半田付けができます。
半田を一度こて先にのせてから付けるところに持っていく方法では、半田のヤニがこて先で焼けてなくなってしまうので、良い半田付けはできません。
5゜製作
・フラッシャー回路基板の作製
基板には部品配置の印刷がありませんので、最初に目印となるICソケットを取り付けると良いでしょう。向きがあるので注意します。
その後は、背の低い部品から順に取り付けます。抵抗、ダイオード*、C4、C2、C3*、トランジスタTr1*、ニチアツの端子*、FET*の順に半田付けしていきます。(*は極性に注意) 部品の向きは図2を参照してください。
標準のキットでは、D3とR8はありません。また、R9とD4は必要な場合に取り付けます。
部品の半田付けができたら、テスト用のリード線を取り付けます。最後に、静電気に注意しながらICを取り付けます。
・発光モジュール部の作製(講習会では省略します)
LEDは比較的熱に弱いので、1箇所あたりなるべく10秒以内で半田付けします。
トランジスタTr2は最大1W近くの発熱がありますので、放熱できるよう周囲を空けておきます。
6゜動作テスト
表示モジュールは、電源につないで発光と電流値を確認します。また、電源電圧を変えても明るさや電流値がほぼ一定であることと、最小バッテリー電圧にしても発光することを確認します。
つぎに、フラッシャー回路に表示モジュールとスイッチを接続し、電源をつなぎます。OUTのスイッチがオフの時、フラッシャーにはほとんど電流が流れていないことを確認します。次に、スイッチをオンして、LEDが点滅することを確認
します。フラッシャーが動作時の電流が1mA以下、待機時の電流が1μA以下であることを確認します。
7゜使用上の注意
バッテリーに接続する配線には安全のため必ずヒューズを入れて下さい。また、フラッシャー回路は内部のインピーダンスが高いのでケースに入れるなどの防水対策をして下さい。また、電源の極性を間違えると、ICとD4がすぐに壊れてしまいます。
問い合わせ先: 鹿野文久 kano@oyama-ct.ac.jp 河西勇二 kasai@etl.go.jp
表1 LEDの特性の例
超高輝度型、径5φ、標準半値角(2θ・1/2)20度以上のもの。
発光色 型名 輝度 最大電流値
赤 GL−5UR3K 3000mcd
赤(無透) TLRH157P 1800mcd 50mA
赤(無透) TLSH157P 2300mcd 50mA
橙 GL−5HJ43 3000mcd
橙(無透) TL0H157P 2000mcd 50mA
黄(無透) TLYH157P 2300mcd 50mA
[付録]点滅周期のやや厳密な計算
T=Ton+Toff
Ton=C×R×ln((VDD+VF)/VTH)≒0.7×C×R
lnは自然対数、VFは、IC内蔵のクランプダイオードの順電圧(0.6V)
C=C1
R=R2 (R8がない場合、または、D3が図面と同じ向きの場合)
R=R2×R8/(R2+R8) (R8があり、かつ、D3が図面と逆の向きの場合)
Toff=C×R×ln((VDD+VF)/(VDD−VTH))≒0.7×C×R
C=C1
R=R2 (R8がない場合、または、D3が図面と逆の向きの場合)
R=R2×R8/(R2+R8) (R8があり、かつ、D3が図面と同じ向きの場合)